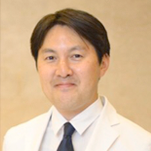下肢静脈瘤の悪化を防ぐためにすべきこと
下肢静脈瘤の主な原因と予防対策
下肢静脈瘤の進行を防ぐために、生活習慣で気をつけるべきポイントとは?
下肢静脈瘤は一度できてしまうと自然に元に戻ることはなく、放置することで徐々に進行し、皮膚の変色や潰瘍などの合併症を引き起こすリスクもあります。しかし、発症や悪化のリスクを高める生活習慣に目を向け、日頃から意識して対策を行うことで、その進行を抑えることが可能です。
特に注意すべきリスク要因として、長時間の立ち仕事やデスクワーク、妊娠、肥満、便秘が挙げられます。これらは、いずれも足の静脈の血液の流れを妨げ、「静脈うっ滞(血液の渋滞)」を引き起こす原因となります。
本記事では、それぞれの原因がなぜ下肢静脈瘤と関係しているのか、またどのような対策をとることでリスクを軽減できるのかについて、血管外科専門医の視点から丁寧に解説いたします。
「何に気をつければいいの?」「妊娠中でも予防できるの?」といった疑問をお持ちの方にも役立つ情報を、今日から実践できる具体的なアドバイスとともにお届けします。
A. 立ち仕事(デスクワーク)
ふくらはぎの筋肉は、私たちの血液循環において非常に重要な役割を担っています。特に、「筋ポンプ作用」と呼ばれる働きによって、足の静脈にたまった血液を重力に逆らって心臓に押し戻すポンプのような働きをしています。このため、ふくらはぎはしばしば「第二の心臓」とも呼ばれます。
しかし、長時間にわたって立ちっぱなしでいたり、逆に座りっぱなしで足を動かさない状態が続くと、この筋ポンプ作用がほとんど機能しなくなります。筋肉が動かないことで静脈が圧迫されず、血液がスムーズに心臓へ戻れなくなり、結果として足の静脈内に血液が滞留してしまいます。
この血液の「渋滞」が繰り返されることで、静脈内の圧力が上がり、静脈の壁が引き伸ばされて徐々に拡張し、やがて静脈瘤として皮膚の表面に浮き出てくることがあります。
日常のなかで意識的にふくらはぎを動かすこと――たとえば、つま先立ちや屈伸運動、足首の曲げ伸ばしといった簡単な動作でも筋ポンプ作用は活性化されます。特に立ち仕事やデスクワークが多い方は、こまめな足の運動を心がけることが下肢静脈瘤の予防に効果的です。
対策
立ち仕事に従事されている方は、同じ姿勢を長時間続けることでふくらはぎの筋肉が十分に動かず、血液が足に滞留しやすくなります。これを防ぐためには、業務の合間に軽く体を動かすことが非常に重要です。とくにおすすめなのが、その場でできる「屈伸運動」や「アキレス腱を伸ばすストレッチ」です。1回につき30秒〜1分ほどでOKですので、休憩時間やちょっとした空き時間を使って取り入れてみてください。
一方、デスクワーク中心の方も要注意です。座りっぱなしの状態は筋ポンプ作用が働かず、静脈内圧の上昇によって静脈瘤を進行させる原因になります。その対策として有効なのが、イスに座ったままできる「足首の曲げ伸ばし運動」や「かかとの上げ下げ運動」です。また、意外に思われるかもしれませんが、“貧乏ゆすり”と呼ばれる小刻みな足の動きも、ふくらはぎの筋肉を刺激し血流を促進するのに役立ちます。見た目は気になるかもしれませんが、静脈瘤の予防には非常に効果的な動作です。
さらに、仕事中に足を動かす時間がどうしても取れない方には、「弾性ストッキング」の着用が強い味方になります。弾性ストッキングは、足首からふくらはぎにかけて段階的に圧力をかけることで、血液の流れを心臓方向へとサポートする医療用のアイテムです。特に下肢静脈瘤の初期症状がある方や予防を意識されている方には、医療機関でサイズを測って自分に合った圧力のものを選ぶことが大切です。市販のサポーターとは異なり、医学的に設計された圧力設計が静脈への負担軽減に効果を発揮します。
【関連記事】【医師監修】立ち仕事の足のむくみ解消法|今日からできる3つの簡単ケア
B. 妊娠
妊娠中は、体内でさまざまな変化が起こるため、下肢静脈瘤のリスクが大幅に高まる時期です。以下の3つの要因が主に関与しています。
1. 血液量の増加による静脈への負担
妊娠中は、赤ちゃんに酸素や栄養を届けるために、母体の血液量が妊娠前より30〜50%も増加します。この増えた血液を受け止めるために、全身の静脈は常に膨らんだ状態になり、特に重力の影響を強く受ける足の静脈には大きな負担がかかります。結果として、血液が下肢に滞りやすくなり、静脈の拡張や弁の機能低下が起こりやすくなります。
2. 女性ホルモン(プロゲステロン)の影響
妊娠中は、女性ホルモンのひとつであるプロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌量が急増します。プロゲステロンには血管の壁を緩めて拡張しやすくする作用があるため、静脈がやわらかく伸びやすくなり、弁もしっかり閉じにくくなるのです。これにより、血液の逆流が起こりやすくなり、静脈瘤のリスクが高まります。
3. 子宮による静脈の圧迫
妊娠が進むとともに、子宮が大きくなっていきます。その結果、骨盤内にある下大静脈や腸骨静脈といった太い静脈が物理的に圧迫されてしまいます。これにより、足から心臓へ戻る血液の流れが滞り、血液が下肢にたまりやすくなるのです。これは、まるで砂時計のくびれ部分で血液の流れが詰まってしまうような状態で、静脈瘤の形成を促します。
このように、妊娠中は静脈瘤ができるリスクが複合的に重なる状態となります。一度伸びてしまった静脈や壊れた弁は、出産後に完全に元に戻るとは限りません。特に2人目以降の妊娠では、初産で弱くなった静脈がさらに悪化しやすいため、早期の予防が大切です。
対策
妊娠中の静脈瘤対策としては、マタニティ用の弾性ストッキングの着用が非常に有効です。足への圧迫を適切にコントロールすることで、血液の逆流を抑え、むくみやだるさの軽減にもつながります。安全性が確保された医療用製品を選び、可能であれば医師の診察を受けたうえで着用することをおすすめします。
【関連記事】妊娠したら弾性ストッキングで下肢静脈瘤を予防しよう!
C. 遺伝
下肢静脈瘤は、立ち仕事や妊娠などの生活習慣による要因だけでなく、遺伝的な体質が深く関与する病気でもあります。実際に、家族に静脈瘤を持つ人がいる場合は、持たない人と比べてはるかに発症リスクが高まることが知られています。
たとえば、以下のような統計データが報告されています。
-
両親ともに下肢静脈瘤を持つ場合:子どもが静脈瘤を発症する確率は約90%
-
片親のみが静脈瘤を持つ場合:
-
女の子が遺伝する確率は約62%
-
男の子が遺伝する確率は約25%
-
このデータは、1969年にスウェーデンのGundersenらが発表した家族集積性に関する研究
(Gundersen J, Hauge M. Hereditary factors in venous insufficiency. Angiology. 1969)に基づくもので、下肢静脈瘤の発症には強い遺伝的傾向があることを示しています。
遺伝するのは、静脈の壁や静脈弁が生まれつき弱く壊れやすい性質であり、何らかの外的負担(長時間の立ち仕事、妊娠など)をきっかけに、その脆弱性が表面化して発症に至るのです。
【関連記事】【専門医が解説】下肢静脈瘤は遺伝する?家族歴がある方必見の医学的データと対策
対策
静脈瘤が「遺伝だから仕方ない」と諦める必要はありません。むしろ、自覚がある人ほど、早い段階から予防に努めることが重要です。
-
日常的に足を動かすよう意識する
-
弾性ストッキングを活用する
-
長時間の立ちっぱなし・座りっぱなしを避ける
-
夕方以降の足のだるさやむくみを軽視しない
-
一度、静脈エコー検査で血流の逆流がないかをチェックする
これらの対策を継続することで、症状の進行を抑えたり、初期段階で治療につなげたりすることが可能です。
D. 加齢
加齢は下肢静脈瘤のリスクを高める大きな要因のひとつです。年齢を重ねるにつれて、血管の構造にも変化が起こります。静脈の壁は、弾性膜や平滑筋(血管のしなやかさや収縮性を保つ重要な組織)で構成されていますが、これらの組織は加齢によって徐々に萎縮(縮んで薄くなる)し、柔軟性や弾力性を失っていきます。
この結果、血管が内側からの圧力に耐えきれなくなり、血液がたまりやすくなるため、重力の影響を強く受ける足の静脈では特に血液のうっ滞が生じやすくなります。静脈にかかる負担が増すことで、逆流防止弁の機能も低下しやすくなり、逆流と血液の滞留が慢性化していきます。
また、高齢になるとふくらはぎの筋力が衰えることもポンプ作用の低下につながり、さらに血液の循環が悪くなる要因となります。
対策
-
長時間の立ちっぱなし・座りっぱなしを避ける
-
ふくらはぎの筋肉を鍛える軽いウォーキングや足首の運動を習慣にする
-
足の重だるさやむくみを感じたら放置せず、専門医に相談する
-
必要に応じて弾性ストッキングを使用し、血液の逆流を抑える
加齢は避けられない要素ですが、早めのケアと日常の心がけ次第で静脈瘤の進行は十分に抑えられます。年齢を理由に諦めず、「気づいた時が最良のタイミング」と捉えて、足の健康管理を始めましょう。
E. 肥満
肥満は下肢静脈瘤のリスクを高める一因となります。
体重が増加すると、足にかかる荷重も大きくなり、下肢の静脈に対する物理的な圧力が増大します。その結果、血管壁や逆流防止弁に過剰な負担がかかり、血液が逆流しやすくなります。
さらに、内臓脂肪の蓄積により腹圧(おなかの中の圧力)が慢性的に高くなると、骨盤内を通る大静脈や腸骨静脈が圧迫され、足から心臓に戻る血液の流れが妨げられます。これは、ホースの途中を押しつぶして水の流れが悪くなるのと同じような状態です。
加えて、肥満の方は運動不足に陥りやすく、ふくらはぎの筋肉が十分に使われないため、筋ポンプ作用も弱まりやすい傾向があります。
対策
-
食べすぎを控え、バランスのとれた食生活を心がける
-
エレベーターではなく階段を使うなど、日常の中でこまめに足を動かす
-
可能であればウォーキングやストレッチを習慣にする
-
足が重く感じる日は、弾性ストッキングの使用も効果的
体重管理は、静脈瘤だけでなく生活習慣病全般の予防にもつながります。「少し太ってきたかな」と感じたら、今が見直しのチャンスです。
F. 便秘
排便時の「いきみ」に注意が必要です。
排便時に強くいきむと、お腹の中の圧力(腹圧)が急激に上昇します。この腹圧は腸を刺激して排便を助ける一方で、腹部にある大きな静脈(とくに下大静脈や腸骨静脈)を圧迫してしまいます。
この状態では、足から心臓へ戻るはずの血液の通り道が狭まり、血流がスムーズに流れにくくなるため、足の静脈内で血液が一時的に渋滞(うっ滞)を起こします。こうした状況が繰り返されることで、血液の逆流を防ぐ静脈弁に大きなストレスがかかり、弁が伸びたり壊れたりする原因になります。
特に慢性的な便秘で毎日のように強くいきんでいる方は、静脈弁の故障リスクが高くなり、下肢静脈瘤を悪化させやすいとされています。
対策
-
静脈瘤を予防するための便秘対策
-
水分を十分に摂取する(1日1.5~2リットルを目安に)
-
食物繊維の多い食事(野菜・果物・海藻・玄米など)を心がける
-
適度な運動(ウォーキングや体操)で腸の動きを活性化
-
便意を我慢せず、自然な排便習慣をつける
-
必要に応じて、医師に相談して便秘薬の使用も検討する
「足の血管」と「お通じ」がつながっているなんて意外かもしれませんが、実は深い関係があります。
便秘がちの方は、下肢静脈瘤の進行を防ぐためにも、日頃から腸内環境の改善を意識しましょう。 -
まとめ:早期予防と正確な診断が大切です
下肢静脈瘤は放置すれば進行し、皮膚炎や潰瘍などの合併症を引き起こすこともあります。弾性ストッキングの着用や運動習慣の見直しといった生活習慣の改善に加え、静脈エコー検査による早期発見が悪化防止の鍵となります。
症状が軽いうちから専門医の診察を受け、正しい予防と管理を行いましょう。
この記事は下肢静脈瘤専門クリニック『目黒外科』院長 齋藤陽 医師監修のもと作成されました。